吉本興業所属のお笑いコンビ・タモンズ。高校時代の同級生だった二人は、2006年にコンビを結成。現在は大宮ラクーンよしもと劇場を主戦場に、大宮セブンの一員としても活動している。
そんな二人が、現在、結成16年以上の漫才師が頂点を狙う賞レース『THE SECOND~漫才トーナメント~』に挑戦中。3月に開催された開幕戦ノックアウトステージ32→16を予選歴代最高得点で勝ち抜き、4月20日(土)、4月21日(日)でのノックアウトステージが控えている。
かつてはヨシモト∞ホールを中心に活動し、順風満帆なイメージもある二人だが、解散の危機に直面していたこともあるそう。彼らのキャリア、そして『THE SECOND』に出場したことで変化した漫才師としての自覚など、ニュースクランチがインタビューで迫った。
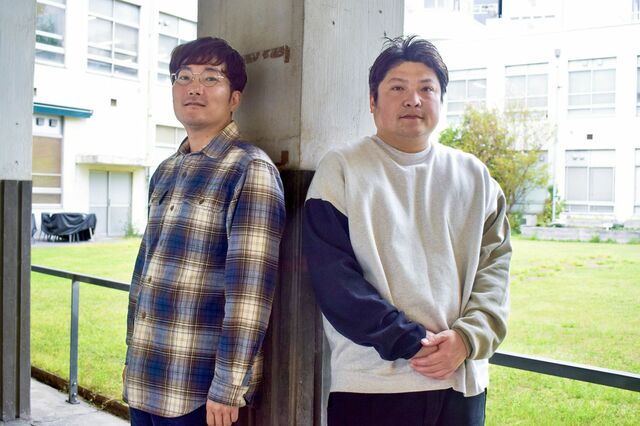
『THE SECOND』初年度の悔しい記憶
――まずは『THE SECOND』初年度の話を教えてください。
大波:選考会ではウケが良かったんですけど、ノックアウトステージに行って、三四郎さんと当たったときにめちゃくちゃ点差があって(タモンズ233点、三四郎254点)、悔しかったですね。
安部:僕らの前が、流れ星☆さんとプラス・マイナスさんの戦いだったんですけど、もうすごくて。ドラゴンボールでいうと悟空とピッコロぐらいの戦い方で、ボケが全然見えなかったんですよ。そのあとが僕らやったんで、お客さんからしたら、そことも比べられちゃったのかなって。
大波:敗退したあとで、選考会の上位8組が入れるポットAに入らないと勝負にならへんし、試合になりにくいなとは思いました。先攻、後攻が意外と影響するなって。
――決勝を見ての感想は?
大波:やっぱり、囲碁将棋がすごかったですね。
安部:すごい大会やなと思いました。囲碁将棋さんみたいな人も、ギャロップさんみたいにしっかりネタをやりきる人も、マシンガンズさんみたいにその場の空気感で臨機応変に対応する人も評価されて。二人で「マシンガンズさんみたいな臨機応変さも兼ね備えつつ、ネタを最初からトップギアでやれる感じで行きたいね」って話をした記憶があります。
――囲碁将棋がベスト4になったことで、大宮の空気感に影響はあったのでしょうか?
大波:それに関しては、何も変わりませんでしたね。彼らとの関係性も、舞台上での立ち振る舞いも。下ネタもバンバン言うし(笑)、こっちが心配になっちゃうくらい。
安部:考えてみれば、大宮セブンって昔からそうなんですよ。みんな売れていないときから始まって、すゑひろがりずとかマヂカルさんがM-1で結果を残し、GAGさんが4年連続でKOCの決勝に進出し、ジェラードンはYouTubeが爆ハネして……あとは、僕らだけ。
定期的に誰かしらが売れていくんですけど、あの団体は持続されているじゃないですか。だから、もう誰が売れようと同じように変わらずにいられる環境なんだと思います。
用意したネタをやるのが漫才師ではない
――初年度の『THE SECOND』のあとで、60分間ぶっ通し漫才をするライブ『詩芸』の全国ツアーを始めましたね。全国ツアーを始めたことで得た気づきはありますか?
安部:漫才のなかで遊ぶようになりました。同じネタをやるのは、僕らも飽きがきてしまうし、一緒に付いて回ってきてくれているお客さまもいるので“違うな”と思って、アドリブを入れたら、ブロックが5~6個ある漫才なのに3個しか消費せず1時間経っちゃう、みたいなことが出てきたりするようになったんです。そういうのを経験して、漫才のなかでどうにか対応する力がついたと思います。
大波:考えてみれば、M-1って自分らが作った作品を見せる、発表する、ということを意識していました。ただ『THE SECOND』に出て、全国ツアーを始めた初期の頃に、もっと“人(にん)”を出さないといけないなって、漫才への意識が変わったんです。
――“人(にん)”を出そうと思ったのはなぜだったんでしょうか?
大波:名古屋でやったときに、めっちゃスベったんですよ。
安部:そう、お客さんが起き上がらないまま終わっちゃったっていうか……。会場が地下街の通勤途中のサラリーマンの方が通るところにあるようなスペースで。夏やったんですけど、空調も効いてないし、ガヤガヤしてるし、僕らもお客さんもなかなか大変な環境やったんです。終わったときに“せっかく来てもらったのに申し訳ないな”って思いました。
大波:それで、用意したものがウケなかったときに、どうするのかを二人で考えたんです。そのときは用意したネタを全部やったけど、暑かったし、ガヤガヤしてるんなら、そこを拾って広げたら、もう少しウケたかも知れないなって。用意したネタをやるのが漫才師なんじゃなくて、極論やらなかったとしても、ウケて終わったほうがいいって考えに変わりました。
ネタに8とか9くらいの割合で重きを置いていたのですが、それ以降はネタ1〜3、残り7は“人(にん)”だなって。ウケなかったときに、漫才師としての引き出しの数を増やす意識が芽生えました。
――逆に言うと、用意したものがウケなかったときにどうするか? みたいなところを考えたのは、昨年が初めてだったということでしょうか?
大波:初めてですね。M-1って出したものが受かるか受からないかだけやったので。ネタに重きを置いていましたから。
安部:腕のある師匠が同じネタを毎回同じようにできることって、本当にすごい技術だと思うんです。ただ、僕はほんまにそれができなくて。今振り返れば、M-1のとき、相方はそれにイラだっていたと思います。
でも、今そこに寛容になってくれたのは、去年の『THE SECOND』を受けて、自由にしてもいいんだっていう余裕が生まれたからかなと。二人とも同じネタを毎回新鮮にできることを、いい方向に捉えられるようになったんだと思います。
――そういうところの意思疎通ができているのは、頻繁にお話しされているからなのでしょうか?
安部:いや……逆に『THE SECOND』が始まってからは、そんなに詰めてないかもしれない。
大波:結局、僕が「ここ行くぞ」ってときに相方が付いてきてくれたり、相方が行こうとしたときに僕が付いていけるかって、板の上で起こった出来事に対してどうするかでしかなくて、事前にすり合わせしても、あんまり意味ないんですよね。だから、終わったあとに答え合わせするくらい。
安部:うん。「あれ合ってた?」「あそこは行かなくてもよかったんちゃう?」って。
大波:そう考えると、今は時間を測る以外はやっていないですね。『THE SECOND』でも、ネタは出番の6組前とかに決めたくらいですから。お客さんの感じを見て。
安部:そんなん言うたら余裕ある感じに思われるかもしれないですけど、僕ら1組目からずっと袖に張り付いてましたけどね(笑)。それに、僕に関していうと、許容範囲が少なくて、パッと言われてできるネタは4つぐらいなので、ものによっては、もう少し早めに言っていただければうれしいなと思っています(笑)。


 NewsCrunch編集部
NewsCrunch編集部