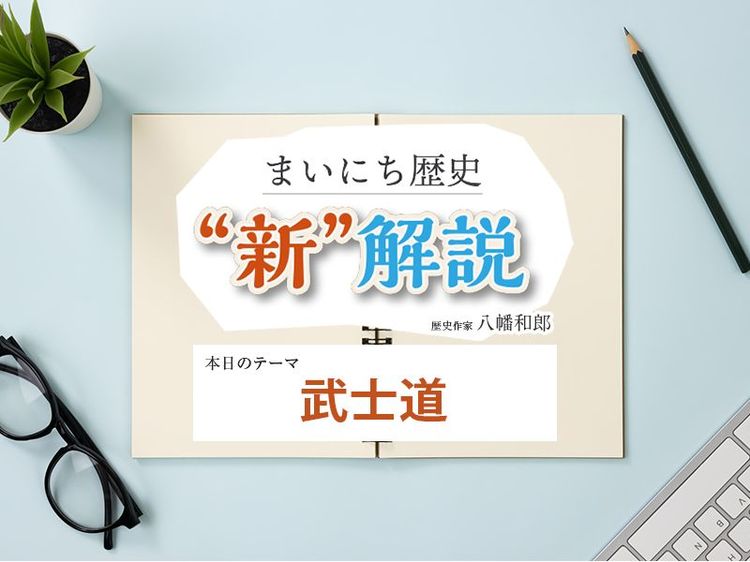セオドア・ルーズベルトと『武士道』
日清・日露戦争を通じて、アメリカは常に日本に好意的でした。とくに、新渡戸稲造の『武士道』に感銘を受けたというセオドア・ルーズベルトは、そのおかげでポーツマス条約(1905年)を有利な形で結ベました。

尚武の人で、勇気に団結力、勤勉や進取の精神を良しとするルーズベルトにとって、日本人が好ましく思えたのは当然のことでしょう。
韓国を日本の勢力圏とすることについて積極的な支持を得ることができ、来日したタフ ト陸軍長官と桂太郎首相のあいだで「桂・タフト協定」が結ばれました。
日露戦争ののち、アメリカが日本を警戒しだしたという意見もありますが、それはアメリカの国力も上がってアジアに利害を持つようになった結果として当然で、態度の急変とするのは適切でありません。
むしろ、米西戦争によるフィリピンへの進出、ハワイ王国の併合、中国市場への進出、パナマ運河の開通、カリフォルニアの発展など、太平洋国家としての道をアメリカが歩み出した結果と言うベきです。
ルーズベルト大統領は、海軍の艦隊を世界一周旅行に出して、日本にも1907年に立ち寄らせました。日本は大歓迎をしたのですが、これをアメリカの示威行動と言う人もいます。どちらの性格もあったというのは普通のことです。
アメリカは「オレンジ作戦」といって、世界各国との戦争のシミュレーションをして、そのなかには対日戦争もありました。このとき、ヨーロッパ諸国についてもシミュレーションしているのですから、一人前として認められたといった程度のことですが、アメリカが日本を将来において戦うかもしれない国の一つとして意識し始めたのは事実です。
あるいは、満州での鉄道経営にハリマンを参加させたらよかったのに、という意見もありますし、そうだったかもしれませんが、アメリカ自身もモンロー主義でラテン・アメリカを自分の勢力圏として扱うのを放棄したわけでありません。
ハワイについては、ハワイ国王が自ら来日して明治天皇に同盟を結ぶことを懇願したのを、同情しつつも謝絶してアメリカによる併合を実質上、容認したりしているわけですから、日露戦争以降の対米外交が強気過ぎて警戒されたとは言えないと思います。
※本記事は、八幡和郎:著『アメリカ大統領史100の真実と嘘』(扶桑社:刊)より一部を抜粋編集したものです。