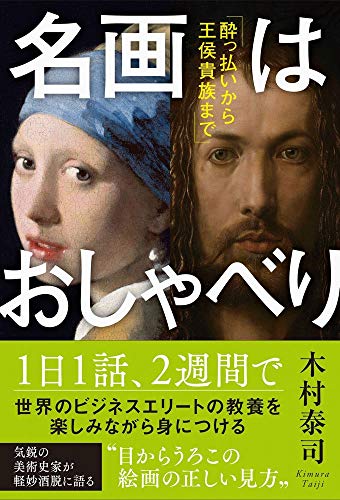波乱な運命を背負ったルーベンス少年
17世紀のフランドルを代表する画家ルーベンスは、実はフランドルではなく、ドイツのジーゲンという街で産声を上げています。プロテスタントだった両親が、迫害から逃れてアントウェルペンから亡命していたのです。
しかし、法律家だった父親が、オランダ建国の父であるオラニエ公ウィレム世の妻アンナと不倫スキャンダルを起こしてしまいます。危うく死刑になるところを、自分が裏切った妻の必死の命乞いのおかげで、なんとか自宅軟禁に収まったといいます。こうして死刑を逃れ、自宅軟禁中にできた末息子が「バロック絵画の王」となるルーベンスでした。1577年6月28日のことです。
彼の誕生は、スキャンダルにまみれた一家に幸運をもたらしたようで、翌年になると父親は赦免され、一家はケルンに移って法律家稼業に戻ることもできました。成人してからのルーベンスは、自分をケルン生まれと称しています。一家の不名誉につながるジーゲンとの縁を断ち切りたかったからでしょう。
父親が1587年にドイツで客死すると、母親は子どもたちを連れて故郷アントウェルペンに戻ることになります。すでに一家はプロテスタントからカトリックに改宗していたため、カトリック圏であるアントウェルペンで暮らすことができたのです。
アントウェルペンでは、ルーベンスは後に古典学者となる兄フィリプスと共にラテン語学校に通いました。当時、ラテン語は上流階級の子どもが受ける教育であって、職人と見なされていた画家を目指す子どもの受ける教育ではありませんでした。このことから、母親がルーベンスを画家にするつもりなど、さらさらなかったことがうかがえます。

ルーベンスのように、当時の国際語であるラテン語教育を受けた画家が描いた画は、内容的にとても奥深いものが多いものです。幼い頃に受けた教育がベースにあったため、彼は高い古典的教養を持った王侯貴族など上流階級の顧客を相手に、同じような知識をもって対応できました。
顧客にとって必須の教養だった古典文学を、同じようにラテン語で読めたというメリットは、現代人には計り知れないものがありました。しかし、13歳のルーベンスは、母子家庭だったため学業を続けることが困難になり、貴族の未亡人の小姓になります。
良家出身で教養もあるが、資産のない若者にとって、出世コースの定番であった小姓勤めを母親が選び、息子に宮廷人になるレールを敷いたのです。
ところが見えない力は、14歳のルーベンスを別の方向に向わせることになります。少年は画家として生きていくことを決意したのです。こうして、ルーベンスは当時の決まりであった7年間の画家としての修業を終えた後、修業の仕上げとして芸術の国イタリアを目指すことにしたのです。
謹んでお悔やみ申し上げます。