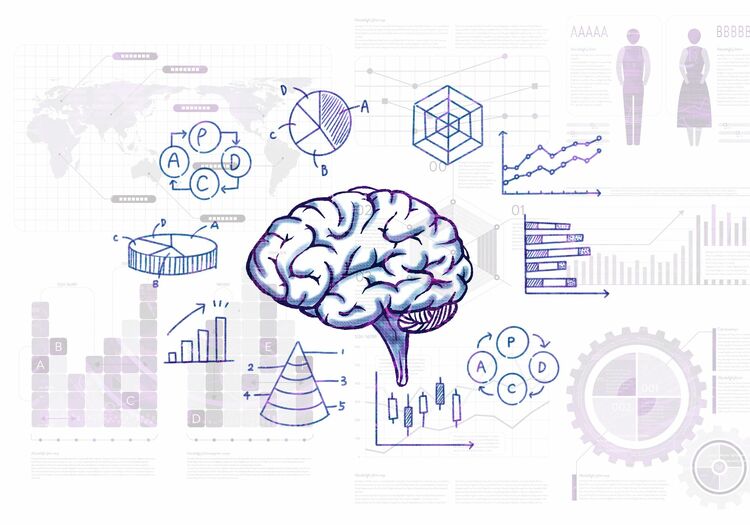薄くスライスしても神経回路は生きている
代替法で、培養細胞や生体組織を利用する方法について述べました。個体の生命が終われば、それを構成していた細胞や組織の生命活動も停止すると思われがちですが、死後も組織はしばらく生き続けることができます。
適切に酸素や栄養を与え続けた環境ですと、数時間生き続けます。それをしっかり培地に生着させ、自活できるようにした状態が培養という状態です。培養細胞は、数日は生き続け、植え継ぎを行うことで、さらに寿命を延ばすことができます。
私が研究対象にしている脳も、しっかりと冷やした状態で摘出し、厚さ0.4ミリメートル程度にスライスしてから37℃に戻すことで、神経回路構造を保ったまま生かすことができます。
脳は、かなり厚みのある臓器で、脳の表面は大脳皮質で覆われているため、大脳皮質以外の脳部位の活動を調査したい場合、脳の深部までを測定するのは技術的に非常に困難を伴います。ところが、脳の深部でも、こうしてスライスして切り出してくれば、簡単に顕微鏡で観測したり、電気的な活動を測ったりすることができます。
また、神経回路構造は保たれているので、神経細胞がどのようなネットワークを作って活動していたのかを知るための、いい手がかりとなります。
したがって、なんでもかんでも生きた動物で実験することが、必ずしも最適な解とは限りません。自分が何を知りたいのかに応じて適切な試料を選択するのが、良い研究と言えるでしょう。
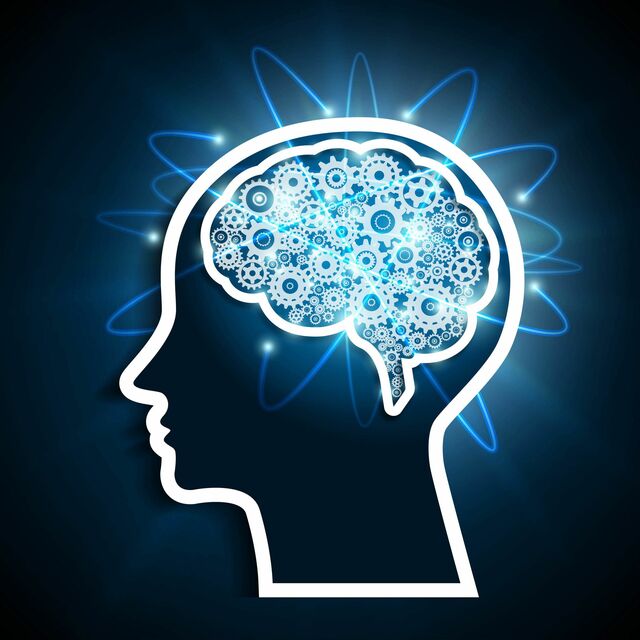
研究のスケールによって異なりますが、生きた動物で行う実験のことを「in vivo」と呼び、摘出した脳や培養した脳、固定した脳で行う実験のことを「in vitro」と呼ぶことがあります。最近では、上述のように摘出はしたけれども、まだ生きている状態のことを「ex vivo」と呼ぶこともあります。
細胞レベルの研究をしているグループでは、摘出した脳であっても、生きた細胞で実験をすることを「in vivo」ということもあるそうなので、その実験がどのレベルの実験なのかを見定めることは重要です。
たとえば、新聞やインターネットで大発見! という見出しで研究成果が報道されることがありますが、よく読んでみたら、摘出した組織切片で行った実験結果だったということはよくあります。用いる実験系に貴賤はありませんが、どのような実験環境で得られた結果なのかをしっかり吟味したうえで、実験結果を解釈する必要がありますし、研究者は誤解を生まないような説明を行う義務があります。
電化製品が始まるきっかけはカエルの観察?
さて、生きている脳細胞の顕著な特徴といえば、やはり電気的な活動をする点にあります。この電気的な情報は実際に測ることができます。
たとえば、脳波は、脳細胞の集合的な電気活動であり、頭蓋骨の上からも測定することができます。脳波は、1秒間にどれくらい波打ったかを表す指標である周波数で分類されています。脳波がゆっくりとしていれば体も眠っていて、逆に脳波が早ければ、集中して思考しているということが類推できるのです。
この脳波測定は、人間から脳細胞の働きを直接記録することができる唯一の手段と言えます。一方、機能的磁気共鳴機能画像法(fMRI)や陽電子放射断層撮影法(PET)では、脳細胞が活動した結果、生じる血流の変化などの二次的な変化を捉える方法であり、急速に進歩はしているものの、未だ神経の電気活動に匹敵するような早い信号を記録することはできません。
脳をはじめとする生体電気信号から、体の状態や生体ネットワークの情報処理などの機能について調べる学問のことを、電気生理学と言います。脳に限らず、多くの細胞は電気的な変化を示します。たとえば、筋肉や心臓の活動を電気的に測定した結果が、筋電位や心電図となります。
生き物の体が、電気的な力を利用して情報伝達しているという事実は、1700年代にイタリアの科学者が、カエルの筋肉の動きの観察から発見しました。さらに、そこから着想を得た別の科学者が、2種類の異なる金属から電気を取り出せることを発見し、電池を発明しました。

以来、多くの科学者が電気現象を熱心に研究した結果は、電磁気学として大成しました。今日の私たちの暮らしが、多くの電化製品の恩恵を受けているのは、実は生物が発生させる電気現象から始まったというのは、少し意外で驚きです。
その後、電気的な測定手法が向上するとともに、電気生理学も切磋琢磨して発展してきました。現在では、ヘッドギア型の装置や、額に貼り付けた簡易的な電極で脳の活動を測定したり、リストバンド型のスマートウォッチで心電図を測定したりするなど、生体信号の測定技術は、目覚ましい進化を遂げているのはご存じの通りです。