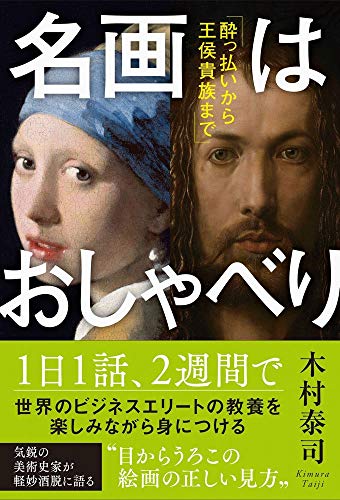「色彩の魔術師」と称されるフランスの巨匠、アンリ・マティス(1869-1954年)。フォーヴィスム(野獣派)の代表格として美術史に多大な影響を与えたあとも、生涯をかけて色と形の探求に没頭しました。現代においてもマティスの作品は私たちを魅了し、次世代の芸術家たちにも深いインスピレーションを提供しています。
南フランスのニースで活動していたとき、彼は「オダリスク」と呼ばれる、ハーレムの女性をモチーフにした絵画を多く描いています。この時代はマティスだけでなく、多くの芸術家がオダリスクの作品を残しました。
上野にある東京都美術館で「マティス展」が開催(2023年4月27日~8月20日)されているこの機会に、20世紀のヨーロッパ美術において、なぜオダリスクが多くの芸術家を魅了したのか。今回の記事では、その歴史的な背景を見ていきたいと思います。
マティスが生きた20世紀初頭のフランス

1869年、アンリ・マティスはフランスのル・カトー=カンブレジで生まれました。当初は法律家を目指していましたが、21歳のときに盲腸炎で療養中に母から画材を贈られたことがきっかけで、絵画に興味を持ちます。
その後、パリの美術学校に進学し、印象派やポスト印象派の画家たちから影響を受けています。1905年には「開いた窓」など、いくつかの作品をパリの美術展(サロン・ドートンヌ)に出品。人気を集め「野獣派」と呼ばれるようになります。色彩や構成を追求し、キュビズムや抽象芸術などの新しい流派にも挑戦しています。
マティスはモローやセザンヌ、ゴーギャンなどの画家から影響を受け、またピカソやドランなどと交流を重ねています。また彼は旅行を好み、イギリスやモロッコなどに赴き、新たなインスピレーションを得ました。
1917年からは南フランスのニースを活動拠点とし、この時期は「ニース時代」と呼ばれ、優美で官能的な作品を多く残しています。1941年には、十二指腸癌の手術を受けて体力が衰えたことで、切り絵の手法を用いた作品を制作するようになります。切り絵作品のなかでは『ジャズ』シリーズが有名です。
1951年から1953年にかけては、南仏ヴァンスのドミニコ会修道院ロザリオ礼拝堂の内装デザインを手がけています。1954年、心臓発作によってニースで死去しました。

マティスの生涯は、産業革命や帝国主義、世界大戦などの大きな社会変動が起きた時代です。産業革命のあと資本主義が発展したため、ヨーロッパでは工業化による大量生産、また製品の余剰(市場の飽和)が問題となりました。
これらの目的を解決するため、ヨーロッパ諸国はアジアやアフリカに次々と侵略。政治的、経済的、軍事的な支配と抑圧を行い、領土と勢力(植民地)の拡大を進めました。これが「帝国主義」と呼ばれる政策です。
帝国主義によってヨーロッパ諸国の植民地が増えていきましたが、同じように広がっていったのが、キリスト教をベースにしたヨーロッパ文化です。日本の場合、戦国時代にフランシスコ・ザビエルなどの宣教師たちが来日して、布教活動をしたことは歴史の授業でも習ったかと思います。
豊臣秀吉や徳川家康などによってキリスト教は禁止されたため、日本では広まりませんでしたが、西洋画の鑑賞をはじめとしてヨーロッパ文化を理解するために必要なのが、キリスト教の知識なのです


 NewsCrunch編集部
NewsCrunch編集部