作品を描くことで自分を浄化させていく
この本を読むと、歯科技工士をしながら漫画家を目指していた時期がある、という記述が出てくる。給与明細を見た姉の夫が、ひっくり返るほどの薄給だったと。
「ただ、それは自分の中では土壇場っていう認識じゃないんですよね。職場の環境も悪くなかったですし、社長さんも奥さんもいい人でしたし、先輩にも恵まれて、居心地はすごく良かった。金銭的な問題はありましたが、それは途中から漫画を描き始めたことで解決しましたし、漫画を描くことを容認してくださいましたし」
そして、伊藤が土壇場について話してくれた。
「それよりも『星新一ショートショートコンテスト』で、箸にも棒にも引っかからなかったのには、こたえました。応募したのは第一回なんですが、あとから聞いたら5000作ほどの応募があったらしく。自分ではせいぜい100作くらいかなと思ってたのと、私も“これは獲ったな”という根拠のない自信があって……ツラかったですね。
挫折といえば、高校のときは美術部だったんですが、友達の肖像画を描いてたんです。不真面目なんで描きながら友達と鬼ごっこしてたんですけど(笑)。そしたら、美術部の先生から“影が濃すぎる”と作品の欠点を指摘されて、めちゃくちゃズシンと来て、そこから当分のあいだ、不眠になりました」
漫画家になってから土壇場について聞くと、少し笑みを浮かべながら、こう答えてくれた。
「それは毎回です。でも、締め切りが迫ってこないと集中できないんです。最初からスケジュールを立てて、一日何ページと決めればいいんですけど、絶対そうはできない。締め切りが迫ってくると焦り始めて、すごい集中できるんです。誰しもがそうかなと思うから、恥ずかしいんですけど…(笑)」
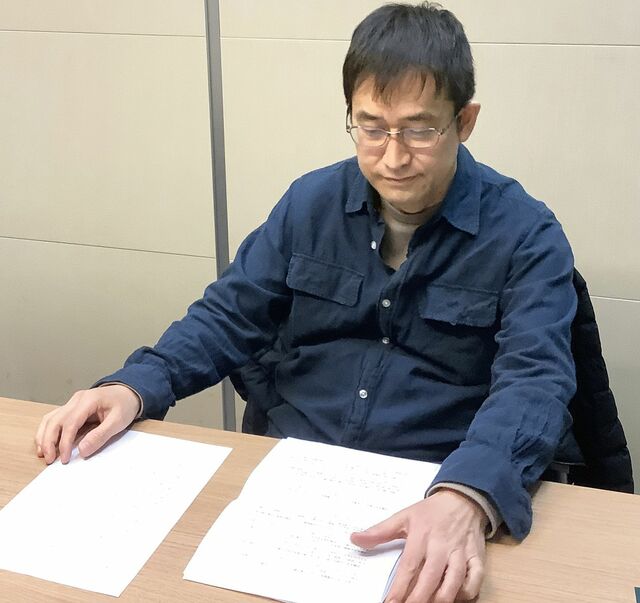
伊藤が現在の土壇場と語る“締め切り”は別として、高校時代の美術部での先生から欠点を指摘されたこと、星新一ショートショートで受賞できなかったことなど、落ち込んだりはするものの、その都度、立ち上がっているのが伊藤潤二なのだ、というのが話を聞いてるとよくわかる。
「向こうっ気は弱くなかったですね。何かを言われても“なにくそ”という思いはありました。デビューしてから、大概の編集者の方は有益なことを教えてくれましたが、たまに“ん?”って思うようなアドバイスは……あえて無視してました(笑)」
本を読んで、歯科技師時代が土壇場なのでは? と思ったのは、単純に収入、そして社会的に認められている場所から遠いからだった。しかし、伊藤はそれを大きく否定した。
「だって、稼いでやろうとか、有名になりたいと思っていたら、もっとメジャーなところに行こうとしますよ。漫画においては好きなことを描きたい。多くの人の薄い評価より、少数でも高い評価を得たかったんです」
では、そんな伊藤の土壇場を乗り越える術は、どのようなものだったのか。
「僕の辞書には、臨機応変という言葉がないんです(笑)。土壇場に巻き込まれると、どうしよう……とあたふたしちゃう。流されて流されて……だから、随分と間違ってきたなと思いますよ」
流されるままであれば、圧倒的な存在になり得ないと思うのだが……。もしかすると、伊藤には“鈍感力”も備わっているのではないだろうか。この本を読んでいると、伊藤の思い出から、他人に対する恨みや怒り、現状に対する不満などは出てこない。かと言って、そういった出来事がないというわけではなく、ただただ、事実としてそれらが列挙されている。
もしかすると、伊藤潤二という人間は、ただただ“いい人なのではないか”、と。すると、同席した担当編集が「本当にそうなんです」と同調したが、伊藤はそれを即座に否定する。
「騙されてますよ、皆さん(笑)。それは、劣等感や嫉妬を表に出していないだけだと思います。自分自身ではコントロールできない部分ですが……。ただ、そういった感情を作品にぶつけたり、作品で昇華させている、という面は大いにあると思います」
「渦巻いている」とも伊藤は表現した。彼の代表作のひとつである『うずまき』を思い出した。
「作品を発表するごとに、自分の中の渦巻いているものが吐露され、自分が浄化されていったんだなと、この本を出版して気づいたことのひとつです。若い頃はもっと作品と人物が近かったような気がします。徐々にそういう渦巻いたものを作品に押しつけていったということかもしれません」


 NewsCrunch編集部
NewsCrunch編集部

