「二人で喋っているのが楽しいから」。高校時代の友人である菅広文と宇治原史規がお笑いコンビ・ロザンを結成した理由だ。漫才師として頭角を現し、バラエティだけでなく、情報番組やクイズ番組などに出演。二人はすぐにお茶の間の人気者となった。
菅が6月8日に発売した『京大中年』(幻冬舎)は、35万部を突破した「京大芸人」シリーズの最新刊である。ロザンが、いかにして現在の場所にたどり着いたのか。過去の相方や自分に「手紙」を通して思いを伝えている。
ニュースクランチ編集部は、新刊を発売したばかりの菅に、京都大学出身の宇治原の愛すべき人柄、相方に「さん」付けして敬意を持って接している関係性。そして、誰にでも役立つ思考と仕事術などをインタビューで聞いた。

俯瞰で見られたのはコンビ仲が良かったから
――この本を「手紙形式」にしたのには、何か理由があるのでしょうか?
菅広文(以下、菅) 最後まで書ききるためには、どういう手法が一番いいのかを考えました。いろんな形式があるなかで、最後まで書ききれる、なおかつ自分の思いがうまく伝わるのは手紙形式やな、と。ただこれは、30代だったら、こっ恥ずかしくて宇治原さんに宛てないまま書いていたでしょうね。それが40代(現在、46歳)になって、うまく消化できた感じです。
――では、40代になった菅さん自身、これまでの「京大芸人シリーズ」と、取り組み方や書き方に違いはありましたか?
菅 『京大中年』を読んだ宇治原さんが「『京大芸人』は処女作なのもあって、自分の思いをそのまま書いている感じ。(二作目の)『京大少年』はテクニカル。『京大中年』は、その二作をうまくミックスしているのがすごいな」とおっしゃってくれて、うれしかったです。書いているときは、そんなこと意識していなかったんですけどね。
――なるほど。菅さんがこだわった部分はどこでしょうか。
菅 『京大芸人』や『京大少年』は勉強、『京大中年』は仕事術みたいな話をさせてもらっているんですけど、3部作共通して「笑かしたい」という思いがあります。「勉強方法」とか「仕事術」とかを使ってはいるけど、どれも「笑かすツールである」という気持ちですね。
――たしかに笑ってしまう箇所がいくつもありました。読んでいて驚いたのが、若手時代の菅さんが恐ろしいほど冷静に自分たちを見つめていたことです。なぜ周りに流されず、ロザンというコンビを俯瞰で見られていたのでしょうか?
菅 やっぱり「コンビ仲が良かった」というのが一番大きいのかなと思います。どのコンビもそうやと思うんですけど、飲みに誘ってくれる先輩ってコンビの片割れだけなんですよ。そこで、先輩・後輩の関係を構築していくんですけど、 我々の場合は、それが終わったあとに「飲み会でこんなことがあった」とか「こっちは、こんなこと言ってた」みたいな話をしていました。
いま思うと、どちらの考えもうまくミックスさせたのがよかったのかなと思いますね。あと、ロザンの特性やと思うんですけど、二人とも(先輩などから)持って帰ってきた情報が一番正しいとは思っていない。その先輩が好きやと「その情報が絶対正しい!」ってなってしまうけど、ウチはそういうコンビじゃなかったなと思います。
――当時としては特殊かもしれませんが、あるべき姿ですね。
菅 どうしてもコンビ間では、力関係の差が出てきてしまうんですけど、(ロザンは関係性が)イーブンなのもよかったかもしれないです。
――だから、相手の話も傾聴できたし、二人が出した決断も「正しい」と言えるんですね。
菅 「正しい」というよりは、二人とも楽観的で「これまでも間違った決断があったやろうな」というのを、自覚してるコンビでもあるんですよ。それはなぜかと考えると「適当やったからちゃう?」みたいな(笑)。
(高学歴芸人と言われることもあるため)全部が論理的に見えてしまうコンビではあると思うんですけど、二人とも根がすごく楽観的だからこそ、気が合うところもある。どちらも論理的やと、ぶつかることも多かったやろうなと思います。


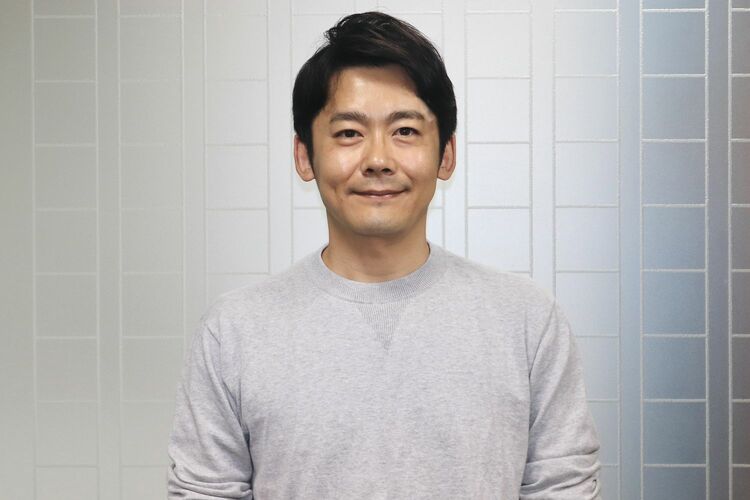
 NewsCrunch編集部
NewsCrunch編集部