「巨人キラー」として知られ、1990年代のヤクルトスワローズ(以下、ヤクルト)黄金期を支えた川崎憲次郎は、中日に移籍後の2004年に現役を退き、現在は野球解説者として活躍しながら、彼の故郷でもある大分県の魅力をさまざまな形で発信している。
いくつもの怪我を乗り越えて、日本シリーズのMVP(1993年)や、最多勝と沢村賞(1998年)獲得などの栄光を手にしたプロ野球人生。それらを成し遂げるために乗り越えてきた「土壇場」のエピソードを語ってもらった。

巨人ファンの野球少年が巨人キラーになるまで
大分県・津久見高校のエースとしてチームを春夏2度の甲子園に導いた川崎は、1988年のドラフト1位でヤクルトスワローズに入団し、プロ野球選手としてのキャリアを歩み始めた。
「高校3年のときには春夏とも甲子園に出場できましたし、九州ではほとんど負けたことがなかった。当時の僕は世間知らずなところもあったので、入団前には“10勝くらいはできるんじゃないか…?”と気楽に考えていたんですけど、実際にプロの世界に一歩足を踏み入れた途端に、厳しい現実をまじまじと思い知らされることになりました。
尾花(高夫)さん、荒木(大輔)さんをはじめとする先輩たちのピッチングを目にすると、その迫力に圧倒されるばかりで。“もしかしたら俺が足を踏み入れるような世界じゃなかったのかも……”と、プロの実力に恐れおののいたことを覚えています」
だが、1年目から先発として起用された川崎は、9月24日の対巨人戦でプロ初勝利を完封で飾ると、その後も4勝(4敗)1セーブの活躍。ヤクルトが名将・野村克也氏を指揮官に迎え入れた1990年には、先発として自身初の2桁勝利(12勝13敗)を挙げたが、巨人の吉村禎章にサヨナラ本塁打を許し、リーグ優勝を決められる(9月8日・東京ドーム)悔しさも味わった。
「かつては熱狂的な巨人ファンだった」という川崎の心には、この試合を境に強烈な巨人への対抗心が宿り、16年間の現役生活で、巨人を相手に積み重ねた白星は29勝(通算88勝)。じきに川崎は「巨人キラー」としても広く知れ渡ることとなる。
「僕が生まれ育った大分県は、巨人戦しかテレビ中継されないエリアでしたから、巨人戦の登板時には、自ずと気持ちが昂っていたように思います。首脳陣からは“打者のインコースを突け”と言われていました。
けれど、当時は今よりも厳しい上下関係があったので、さすがにそれは難しかったです。でも、“かつてテレビで応援していた選手たちに、自分の力を知ってもらいたい”という気持ちで、とにかく全力で投げることを心がけました」
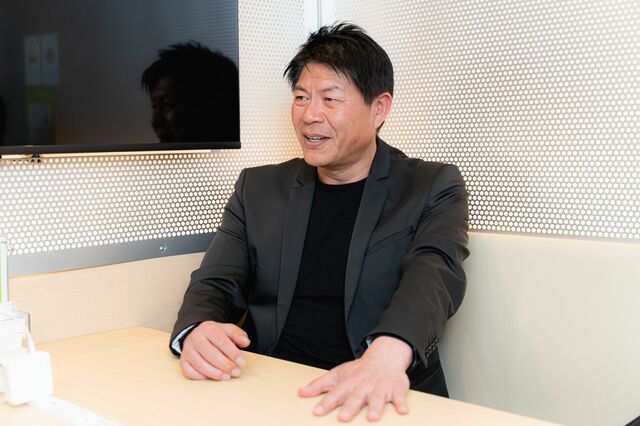
ボールを10cm変化させることで叶った夢
強気な投球でチームを牽引した川崎は、1991年も14勝を挙げ、ヤクルトの11年ぶりのAクラス入りに貢献。翌年もさらなる飛躍が期待されたものの、キャンプ中の怪我によって、一軍未登板のままシーズンを終えることとなった。
だが、川崎が不在のヤクルトは、苦しい投手事情をやり繰りしながらも阪神とのデットヒートを制してペナントを奪取し、14年ぶりのセ・リーグ優勝を掴み取った。
「前年まではそれなりに活躍してきたはずなのに、1992年は怪我をしたせいでリーグ優勝の歓喜の輪に加われなかった。それが何よりも悔しかったです」
さまざまな試練を乗り越えてきた川崎だが、現役生活で印象に残る「土壇場」のひとつは、ヤクルトが日本一に輝いた1993年の日本シリーズの第7戦だという。
この年、2年ぶりに戦線復帰を果たした川崎は、先発として10勝をマークし、ヤクルトのセ・リーグ連覇に貢献、カムバック賞も獲得した。そして、その年の日本シリーズでは、先発として2試合に登板。優勝を懸けた第7戦でも安定した投球を披露して、チームの日本一に貢献した川崎は、この年の日本シリーズMVPにも選ばれた。
「前年の無念を晴らしたいという気持ちと、憧れの日本シリーズで投げられるうれしさが入り混じったマウンドでした。いま改めて振り返ってみると、僕らが常勝西武を倒したことが、プロ野球の歴史の転換点になった瞬間だったように思えるんです。壮絶な試合でしたが、さまざまなツラい経験を乗り越えたからこそ、良い結果を引き寄せられたのではないかな」
1993年にカムバック賞を獲得して復活を印象づけた川崎だったが、翌1994年は6勝(9敗)と低迷。その後も怪我などで思うような成績を残せず、自分自身でも変化の必要性を感じていた頃、川崎の脳裏をよぎったのは野村監督の言葉だった。
「たしか1995〜6年頃だったと思うんですけど、野村監督が“シュートを投げてみろ”としきりに言うようになったんです。僕が渋っていると“ボールが内角にたった10cmズレるだけで、どれだけ打者が苦労するか。お前ら投手はわかるか?”と重ねてボヤいてくるんです(笑)。当時の僕は、まだまだ“速球で三振を取りたい!”という気持ちも強かったので、しばらくその言葉を聞き流していました。
でも、三振が奪えなくなってきている自分の状況に危機感を感じるようになってきて、思い切って野村監督に騙されてみるか、と思ったんです。現役時代に3冠王を獲得した野村監督も、シュートを苦手にしていたみたいですね」
“再ブレイク”を果たした川崎は、1997年には先発としてチームの日本一に貢献。1998年には17勝(10敗)を挙げて、最多勝と沢村賞のタイトルを獲得した。
「シュートを投げ始めたのは1997年のシーズン途中からでしたが、最初はほとんど誰にも気づかれていませんでした。でも、1998年のオープン戦が始まった頃から、少しずつ新聞の見出しに出るようになって…(笑)。
バレると対策されちゃうじゃないですか。それでもしばらく黙り続けてたんですが、結局シュートを投げています、と公に打ち明けたのは、その年の5月頃だったと思います」
右打者の内角をえぐり、ゴロを打たせて取る「シュート」を覚えたことで、川崎の投球スタイルにもさまざまな変化があったという。
「内角を攻めるという点では、“とても便利なボールだな”と思いました。三振を取りたいという気持ちを捨て、新たな投球スタイルを構築するまでには葛藤もありましたが、1年間しっかりローテーションを守るためには、打たせて取りながら球数を減らすことも考えなければならない。
僕の場合、もしシュートを身につけていなかったら、おそらく最多勝や沢村賞は獲得できなかったと思いますし、もしかしたら徐々にフェードアウトして、そのまま世間から忘れ去られていたかもしれない。ボールをたった10cm変化させるだけで、いくつもの夢を叶えられましたから、“野村監督に騙されてよかったな”と思っています」


 NewsCrunch編集部
NewsCrunch編集部