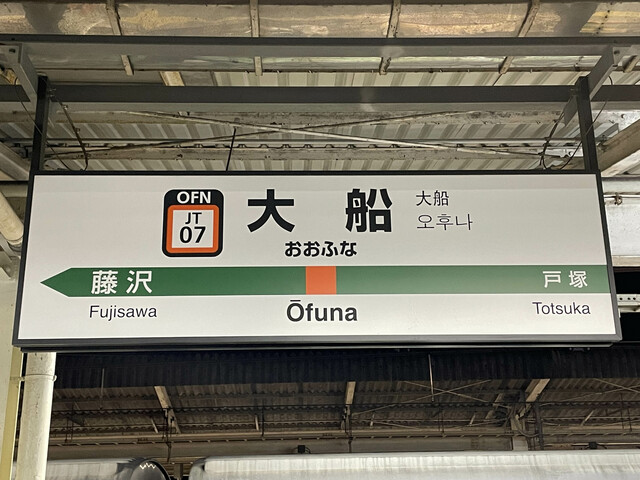神奈川県の鎌倉市と横浜市をまたぐ大船駅には「学問の街」と「下町」の顔を持ち合わせており、老若男女が集うエリアとして人気です。前回、その歴史と街並みのレポートをお伝えしたところ予想以上の反響があり、あらためて大船の人気ぶりを再認識しました。今回は実際に大船駅の周辺を街ブラして、その魅力をさらにお伝えできたらと思います。
〇大船駅前にパチンコ店が新規出店という情報を聞きつけ現地に行ってみた!
「学問の街」として大船の文化を発信する『鎌倉芸術館』
まずJR大船駅の東口改札を背にして10分ほど歩くと、『鎌倉芸術館』が見えてきます。
入口付近に芸術作品が並ぶ大変立派なこちらの施設は、1993年(平成5年)10月1日に開館。中央には竹林が美しく立ち並び、大小ホール・ギャラリー・集会室・和室などを備えており、市民の文化を育み、発信する場として愛されています。
実際、この日も館内では児童たちが描いた作品が展示された「児童画展」が開催されており、多くの人が足を運んでいました。そのほか館内には「京都きもの市場」「銀幕上映会」「鎌倉童謡の会」「よしもとお笑いライブ」「海援隊トーク&ライブ」など多種多様な催し物のチラシがあり、いずれも興味を引くものばかり。もちろん「観る」だけではなく「貸し出し」も行なっており、自身の作品を展示したり、歌や演奏を披露したりすることもできるそうです。
また芸術館の入口の付近のカフェでは美味しい料理やスイーツはもちろん、名産『鎌倉ビール』も販売されており、仕事(取材)で来たのに思わず一気に飲んでしまいました。大きな特長はその豊かな香りと芳醇な味わいで、「何かが違うこの旨さ!」とうなってしまうこと間違いなし。芸術館にお立ち寄りの際には贅沢に昼ビールもぜひ。

「下町」として大船のぬくもりを伝える『大船仲通商店街』
次に街ブラしたのが『大船仲通商店街』。『鎌倉芸術館』から大船駅に向かって8分ほど戻るとぶつかる商店街で、大船駅と並行する形で並んでいます。長さにすると300メートルにも及ばないコンパクトな商店街ですが、その顔ぶれは〝鎌倉のアメ横〟と言っても過言ではない賑わいぶり。両脇にはお肉屋さん、魚屋さん、お菓子屋さん、酒屋さん、そして居酒屋さんも含む飲食が所狭しと軒を連ね、地元住民や学生たちの胃袋を支えているようです。

せっかくの機会なので、昼食は商店街の中からチョイスすることに。悩んだ末に選んだのは商店街の端に位置し、看板の〝手打うどん〟の赤い文字が目立つ『運ど運屋(うどんや)』さん。入口からどこか懐かしい雰囲気が漂っているのですが、実際に店内もアットホームな雰囲気でお客さんを優しく迎えてくれます。
周りを見渡すと「カレーうどん」を頼む方が多かったのですが、すでにビールを飲んだ影響で天ぷらが食べたくなったので「天とじうどん」を注文。出てきたうどんはまさに手打ちでコシがあり、海老天も揚げ立てサクサク。スープも出汁がきいた王道のしょうゆ味であっという間に完食! 店員さんの対応も心地よく、次は絶対にカレーうどんを食べることを誓って店を後にしました。

ちなみに、店内でたまたま隣の席に座っていたおじいちゃんから、「大船仲通商店街はみんな仲が良くて春夏秋冬さまざまお祭りやイベントがあるので、夏になっても必ずおいでよ」と教えていただきました。この記事をご覧の皆さんもぜひこちらの商店街から下町のぬくもりを感じてください。
わずか1カ月でグランドオープンの気配が一気に強まる!
その後は商店街の反対まで歩いてみようと街ブラを続行すると、どこか見慣れた景色に。
そう、前回の記事で発見した「パチンコ出展予定地」の看板が立つ2か所のエリアでした。これは工事の進行状況をのぞきにいかねば! 横浜銀行の正面のコンパクトな土地こそほとんど変化はなかったのですが、駅から芸術館通りを進んだ右手にある場所はわずか1カ月で5階立ての立派なビルに変貌を遂げており、グランドオープンに向けて順調すぎるぐらいに工事が進んでいる様子。外壁には新しいガラスがはりめぐらされ、ちらっと1階の中をのぞくと上に昇る階段もすでにできていました。


この勢いなら夏にはオープンできそうな気配を感じるとともに、ここからどのように内装が施され、パチンコ台・パチスロ台が運び込まれていくのか大いに気になるところ。とはいえ、街ブラで得られる情報はここまでなので、建設主に問い合わせと取材のメールを送ることに。その結果にまた動きがあればお伝えしていきたいと思います。
あいにく、この日は16時から都内で別の仕事があるため泣く泣く新宿方面行の湘南新宿ラインに乗り込みます。次回は鎌倉駅の江ノ電バス亭「大船行政センター」から鎌倉駅に向かうことを決心して、この日も大船を後にしたのでした。


 Newsクランチ!編集部
Newsクランチ!編集部