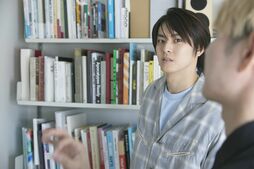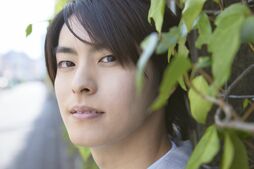アーティストでもあり俳優でもある高野洸が、対談を通してアートの世界に触れ、表現を学ぶ「お訪ねアトリエ」。今回のゲストは、辻尾一平さん。
包んだ物をパンにしてしまう包装紙や、コーヒーを注ぐと珈琲という文字が現れ、牛乳を注ぐと牛乳という文字が現れる珈琲牛乳のグラスなど、日常的に触れるような物を思いもよらぬ視点で、ユーモラスにアップデートするような作品を作るグラフィックデザイナー・辻尾一平さん。学生時代のエピーソドから、作品の制作過程や行動指針についてなど、具体例といっしょにお話いただきました。
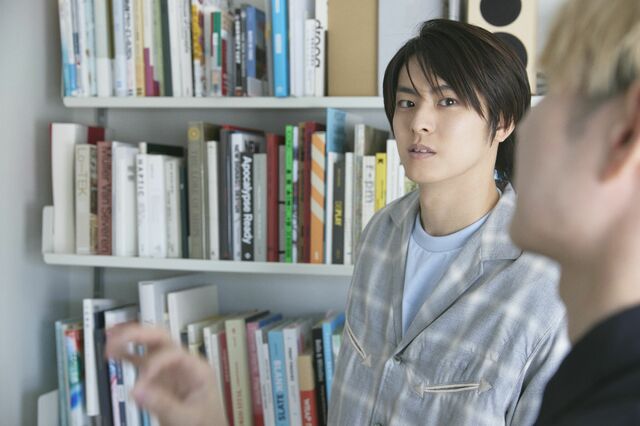
学びを吸収する貪欲さ
――辻尾さんは、子供の頃からなにか作ることが好きだったんですか?
辻尾:実は、全然そんなことはなくて、明確に今の仕事を意識したのは、美大に入るタイミングでした。中学生の頃は、とにかく勉強しておけば、何かになるかな? みたいな考え方で勉強をしてたんです。高校は、進学校に入ったんですけど、そこで、この勉強って何のためにしているのかな? とか。何の役に立つんかな? っていう疑問が生じ始めて、そこで急にモチベーションがなくなってしまって。
やっぱり目的がないと頑張れないなと思っていた頃に、ちょっと落書きから始まって、色々絵を描き始めたんです。でも、絵を仕事にしたいって言えるほど自信も無くて、デザインだったら、まだ食いっぱぐれないかなというイメージがあり、デザインの方に進みました。なので、高校3年生から急に意識した感じですね。
高野:その頃は、今作っているようなものを作ろうっていうイメージとかあったんですか?

辻尾:特になかったですね。僕は、なんとなく商業のイメージができたグラフィックデザインを学び始めるんですけど、その途中で、プロダクト系に興味が沸き始めて。プロダクト系の別のクラスの授業に僕の席を設けてもらったり、別の学校に行ってみたり、そこから色々学んで今では両軸でやっているという感じです。
高野:なるほど。限定せずに、興味を持ったものをどんどん作ったりとか、試したりとかっていう感じなんですか。
辻尾:そうですね、そんな感じでしたね。吸収できるものは全部取り込んでやろうぐらいの感じでやってました。
高野:影響を受けた作家さんとか、デザインっていうのはありますか?
辻尾:影響を受けたのは、nendoの佐藤オオキさんですかね。強いビジュアルを作るタイプの方ではなくて。仕組み寄りのデザインにするというか。当時、僕は、“そんなやり方があるんだ!”って、すごく衝撃を受けまして。僕の制作物も、そういう感じがちょっとどっかに残ってたらいいなと思って作っています。
高野:なんかわかります。
辻尾:デザインにもかなりいろんなタイプの方がいらっしゃって、意匠的な作品を作る人もいれば、仕組みに寄ったようなものを作る方もいて。僕は、見た目の強さよりは、仕組みの部分とか、ロジカルな部分で作品を作ることが多かったですね。今も引き続きそんな感じです。

高野:すごいですよね。知識がないと作れないものも多いと思うので、本当にすごいです。さっきのアロマディフューザーみたいな、科学的なことはデザインのために勉強したわけじゃないですよね?
辻尾:興味本位でこれ面白いなと思ったものは、情報としてメモしておいて、それがいつか結びつくのを待っているみたいな状態ですね。やっぱり自分が直感的に感じた面白さ、外部から受けたものって、自分の中では出てこない面白さがあるというか。それをうまく物につなげた上で、商品として展開していくみたいなプロセスで作っていることが多いですね。
高野:たくさんの世界初を作っていると思うんで、これ本当にすごいことだと思うんですよね。
――辻尾さんは、作りたかったものが完成した時、『よっしゃー!』みたいに、感情が高ぶったりしませんか?
辻尾:そんなに感情が爆発するみたいなことはあんまりないですね。“よしよし、うまくいった“ぐらいの感じですかね。たとえば、グラスのアイデアのきっかけになったのは、パソコンの画面についたホコリなんです。電源を切ったときに、意外とホコリが目立つことってありますよね。そういう気になることをメモしておいて、グラスのアイディアを出す時に見返すんです。
この現象って、もともとそこにあるものが、背景の色によって見えたり見えなかったりするってことなんですよね。そういう現象を、グラスでも表現できるんじゃないかと思って。最初は、黒い文字がコーラを入れると消える、みたいな仕組みを考えました。でもそれだけだとちょっと物足りないなと思って、白と黒の2色にしたらどうなるかと考えました。例えば、牛乳を入れたら白い部分が見えて、コーヒーを入れたら黒い部分が消える、みたいなことができるかもって。
さらに、牛乳とコーヒーを混ぜたら「珈琲牛乳」っていう表示されるようにすれば、一つのアイデアで三通りの楽しみ方ができるなって思ったんです。そういう着地点が見えてきたので、「よし、これでグラスを作ろう」となりました。


 高野洸
高野洸