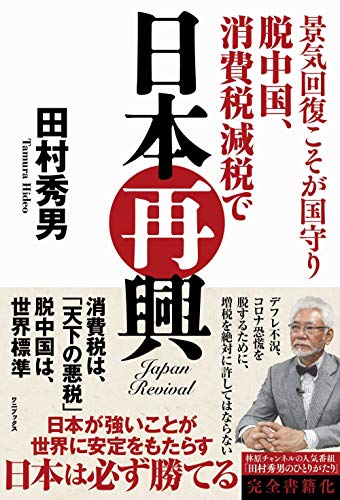習近平政権は、EVやAI、5Gなどの将来性のある分野の普及に向け、外資の投資を催促しています。いずれも軍事に転用されうる最先端技術をともなう分野です。日本企業が中国にビジネスチャンスを求めて、最新鋭技術を携えて対中投資をするのは、軍拡や人権侵害をともなう中国の全体主義路線を助長することにもつながる危険性があると、経済一筋50年のベテラン記者・田村秀男氏は警鐘を鳴らす。
日本企業に根強く残る中国市場への“幻想”
おカネの問題に関して、中国は日本に大きな期待を寄せ、あの手この手を使って中国への投資を呼びかけています。しかし、日本の企業は中国側の甘い誘惑に乗るべきではありません。中国経済に対しても甘い“幻想”を抱くべきではありません。
これから先、中国に投資をする場合には、政治的なリスクのみならず、経済的なリスクも見据えた現実的な判断が必要になってきます。

安倍政権時はコロナショックを機に、産業界に「脱中国」を呼びかけるようになりました。新型コロナウイルスの感染爆発で中国でのサプライチェーンが寸断したことを受け、生産拠点が集中する中国から日本への国内回帰や、第三国への移転を促しています。
2020年度第一次補正予算では、緊急経済対策の一環として総額2435億円を盛り込み、生産拠点を国内や第三国に整備する場合には、建物や設備導入費用の一部を補助することを決めました。

しかし、主要企業の間では脱中国のムードはあまり盛り上がっていません。むしろ、対中投資を増やす動きすらあります。まさに「笛吹けど踊らず」です。もちろん政府も、これからもっと予算を積んで「脱中国」支援を手厚くしていく必要はあるでしょう。
次のグラフは、日本企業の設備投資を中心とする対中直接投資の推移です。投資実行額から投資回収分を除いた「ネット投資」と、投資回収額を投資実行増額で割った比率を追っています。
基準となる投資額は各年4月までの12カ月合計です。投資回収額は、現地の子会社から本国の親会社への収益還元が主体です。日本企業の対世界全体の投資回収比率は7割前後なのですが、こと中国に関しては2019年まで3割にも満たず、極端に低くなっています。
その傾向はさらに加速しており、2020年4月には単月ベースで14%にまで落ち込んでいます。2019年4月~2020年4月の1年間でみてもわずか17%に過ぎません。他の地域では投資実行額を増やしても、同時に回収分も増やすのでネット(正味)の投資はさほど増えないのですが、対中国だけはネット投資が増加し続けています。
安倍政権が「脱中国」企業支援を打ち出した2020年4月でも、投資実行額は前月比で405億円、ネット投資は664億円それぞれ増えています。
一方、回収額は258億円減っているのですが、投資回収を手控えるのは、その分、現地への再投資を増やすことを意味します。つまり、相変わらず日本企業は「世界の工場」中国にどっぷりと浸かっているというわけです。
新型コロナウイルスのパンデミック後も、対中ネット投資を上積みするのは、日本企業の姿勢が中国に対してより協力的になっていることを示します。
対中投資は軍拡や人権侵害を助長することにもなる
その代表的な企業はトヨタ自動車です。トヨタ自動車は2020年2月末、中国・天津に総額1300億円を投じ、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)など環境対応車の生産工場を建設する方針を固めました。
また、6月には中国の大手5社と、水素燃料で走る燃料電池車両(FCV)の中国での普及を目的とした新会社設立の合弁契約を締結したと発表しました。

この動きは、最先端の燃料電池の技術を中国に渡してしまう恐れにもつながります。燃料電池は今や軍事関連の一番のコア技術になっています。ミサイルやレーダーなど、あらゆるものに応用が利くからです。それを中国に渡すことほど恐ろしいことはありません。
こうした日本企業の動きの背景には、やはり日本の主要企業の間で中国経済への“幻想”が一向に弱まっていないという現実があります。
習近平政権は、EVやAI、5Gなどの将来性のある分野の普及に向け、外資の投資を催促しています。いずれも軍事に転用されうる最先端技術をともなう分野です。加えてAIは、共産党政権が弾圧してきたウイグル人やチベット人などの少数民族への監視体制を強化するための主力技術にもなります。
日本企業が中国にビジネスチャンスを求めて、最新鋭技術を携えて対中投資をするのは、軍拡や人権侵害をともなう中国の全体主義路線を助長することにもつながります。今後の中国の動向次第では「日本の民間企業が勝手にやったこと」では済まされないような国際問題にも発展しかねません。
また現在、アメリカを中心に西側世界で広がる対中警戒と脱中国の流れにも逆行するので、中国市場以外でのビジネスチャンスを失うリスクすらあります。これからは日本政府のみならず、日本の企業も、中国に協力的な姿勢がもたらす“親中リスク”をしっかりと認識すべきです。