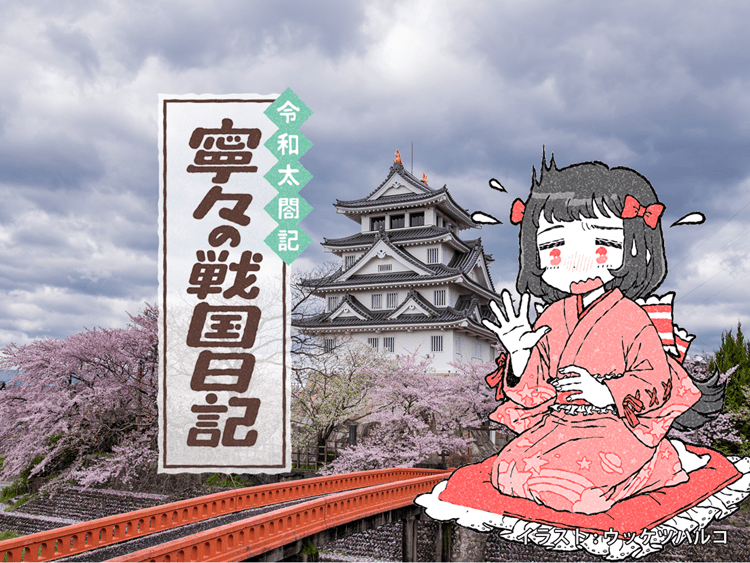
暮らし・教養
犯罪者を使って一晩で城を建てちゃった秀吉伝説ってホント!?
令和太閤記「寧々の戦国日記」:第14回
秀吉の妻・北政所寧々の回想で綴る戦国日記。墨俣一夜城などの秀吉伝説はどこまでホントだったのか。また義父である斎藤道三が心配するほどだった信長のうつけぶりとは?
2021.9.2
配信は終了しました
「うつけ」だった信長を心配した斎藤道三
信長さまが美濃攻めにこだわられたのは、奥方だった帰蝶さまが美濃の国主だった斎藤道三さまの娘だったからでございます。
斎藤道三さまは、山城国山崎...
