バッハとシェーンベルクを中心とする西洋音楽史を講じ、現在は明治学院大学名誉教授、そして指揮者としても活動する樋口隆一氏。そんな樋口氏の祖父が、2万人のユダヤ人を救った“もう一人の東洋のシンドラー”と呼ばれる樋口季一郎陸軍中将である。

近年の研究では、ポーランド駐在武官時代の樋口季一郎は、同国を中心に対ソ諜報の布石を打ち、参謀本部第二部長時代にはバルト海沿岸の対ソ諜報網の拡充を行っている。
樋口季一郎が、半生を通じて「ロシア独自の侵略観とはなにか」を学んでてきた過程を、一見おもしろおかしく綴ってきた記録でもある回想録は、プーチンによる突然のウクライナ侵略に驚かされている現在、学ぶところが少なくないかもしれない。
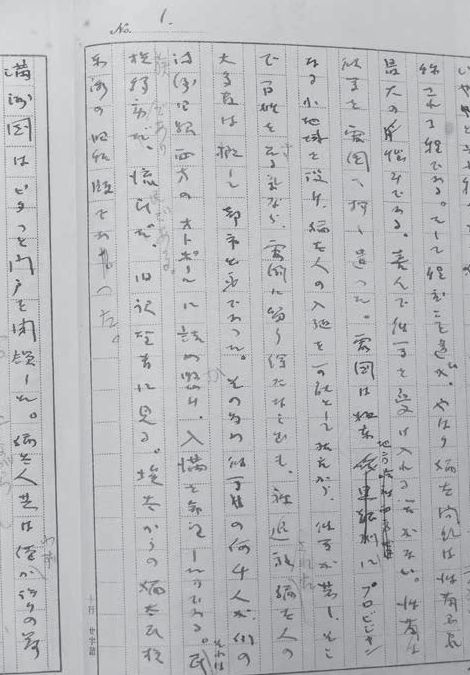
樋口は、大正十四年(1925)ポーランド駐在武官としてシベリア経由ワルソーに赴任した。彼の多芸にしてデモクラティックな性格は、この駐在武官時代に開花し、大尉から新鋭の少佐時代に、若冠にしてはすぐれた駐在武官としての業績を残している。駐在3年有余の後半は夫人を招致し、夫人も外交官夫人としての職責を果たしている。
それでは、ポーランド駐在武官として活躍した樋口季一郎の「大正デモクラティックサーガ」の旅に同行してみよう。
国際寝台列車でモスクワへの旅
大正十四年春、私はポーランド大使館附武官に補任されたので、赴任すべく東京でいろいろと準備にとりかかった。私の一番心配であったことは食物である。私はあまり肉食を好まぬほうである。
ウラジオでユダヤ人の宅に下宿していたときも、夕食の肉料理にはいつも閉口した。ハバロフスクでワシリーと呼ぶ支那人のコックの作る、あまりにも濃厚なロシア式料理にも参った。それでも、そのときは米があり、淡泊な料理を楽しみ得た。今度はそうは参らぬであろう。
聞くところによれば、イタリア米が自由に輸入されるから、米の問題は心配に及ばぬが、日本料理の材料は東京で準備して行ったほうがよいと、ポーランド独立後、駐在せる初代の武官山脇少佐(後の陸軍次官、大将)の忠告であった。そこで私は菊屋に、味噌、醤油、各種魚類の缶詰、海苔、漬物、福神漬等を三箱ばかり注文した。
ディプロマのパスポートのおかげで、それらの品物はハンブルグ経由、私のワルソー到着後まもなく安着した。
大根の「香の物」の缶詰はちょっと面白い。内地では想像もつかぬものである。もしそれを開缶したとすると、そこにはとても想像もできない、色の悪い漬物を発見するであろう。私はこれを大事にして味わった。来客などにはもったいをつけて、二切れ以上は差し上げぬこととしていた。
私の最もよかったと思ったのは、簡易スープ(吸物)の内容であった。それは、えび煎餅を主材とし、各種の材料と食塩、味の素を含んでおり、その煎餅包一個を食器に入れ熱湯を注ぐと、すぐに香りよき、日本色濃き吸物椀ができるわけであった。
某日、私はハルピン名古屋ホテルの客となり、このあいだに先輩の助言で、私はシベリア旅行のため旅行用の食器をもとめることとした。革命前、この鉄道にはインターナショナル・ワゴン・リ(国際寝台列車)が運行されており、立派な食堂車も連結されていたと聞くが、今度の旅行のごとく、処々の駅でロシアの婦人の販売するパン、鶏の丸焼、果実などを買いながら、自室で食事をとることも大いに楽しみである。

食いかつ飲むことなどで時間をとることは、この退屈なる十何日かの旅行では唯一の仕事であり、快楽であるからである。私のこの旅行は、革命後の不自由を予想させるに充分である。私はハルピンでも食品店で各種缶詰、紅茶、砂糖、食塩などを買い求めた。
それで直径一尺五寸(約45cm)ぐらいの竹籠が一杯に満たされた。私はそのほかに、ブリキ製の安価な湯沸しをも準備した。

某日、私は満州里駅頭に立った。モスクワ行の列車は満州里駅を始発としていた。私は「ミヤフカヤ・カテゴリア」に乗った。それは「柔種」である。一般的に訳すれば一・二等車である。
当時、ロシアの車の等級は、この柔種と硬種の二種であった。昔のロシアでは四等級があった。四等車は苦力、下層民の常用のためであった。このときは一・二等が柔種であり、三・四等が硬種であった。座席の硬柔から来た名称である。一・二等は実質上では多少の差はあるが、それを同一のものと見做したようである。運がよければ一等席を占有し得るわけであった。私は旧一等を割り当てられた。
それでは「柔」「硬」の二種にせず、一、二等の二階級にすればどんなものか。ところが、当時は「等」「級」なる語、または文字は極度に忌避されたものである。
しかし、汽車旅行する場合、誰でも勝手に好む座席を占領せよ、では社会的秩序が立たぬ。いわんや、外国をして新国家ソベーツカヤ・ロシアを承認せしめんと努力しつつあったときだから、旅行外人の便益も考えなければならず、国内の秩序も示さねばならない。やはり「クラス」に関する内的概念を捨てるわけにはいかぬ。
そこでソベートの指導者は、カテゴリアなる、百姓どもの聞いたことも考えたこともない言語をもってきたものである。カテゴリアはクラスではない。クラスはブルジュアズヌイ・プレードラスートク(ブルジュアの偏見)にもとづく観念であるが、カテゴリアはしからずである。
しからばそれは何か。いわく言い難しで「けり」であった。それでロシアの下層民は満足し、彼らの欲求したラーヴェンストウォ(平等)が実現されつつあると歓喜したものである。それはやはり言葉上のトリック以外の何ものでもない。どこかの「戦力なき軍隊」の類であろう。
近代革命思想乃至革新思想は、ルーソーの「民約論」に発すといわれる。それはリヴァティ(自由)、エガリテ(平等)、フラテレイテ(友愛)の三原則の上に構成されている。
ルーソーといえども、一種簡単な気持ちで、この三大要素を考えたものであろう。これをあるべき精神的傾向となすならば、必ずしも矛盾撞着(どうちゃく)は感ぜられないが、真剣に考えると到底、相容れない要素を含んでいる。
特に自由と平等の二者の関係である。ソベートにおいて、いかに自由が害されているか。アメリカにおいて、いかに平等が没却されているか。それでも英・米人のあいだにおいては「自由」がスムーズに伸び育つ関係上、「平等」に関する不足が補われているのである。
わが日本において「平等」を主張する立場の人々は、その本質を思わずして自らの地位のみを主張し、もって平等観を正視し得たりと考えてはいないか。また、自由を主張する立場の人々は、真の自由を思わずして「放任」「放縦」をこととしてはいないか。これでは左右正面衝突以外に行き方はないであろう。考えてみればルーソーも罪な哲人である。




