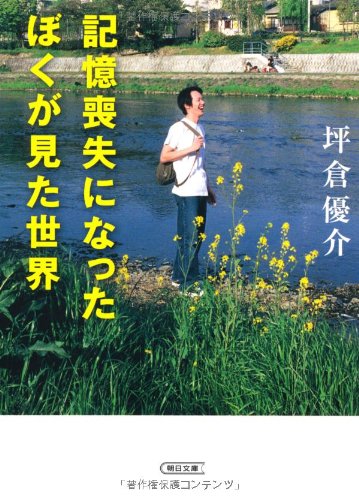「あたらしい過去」を生み出そうとする決意
1989年6月5日。雨が降る日の夕方、帰宅途中に乗っていたスクーターが、トラックに衝突。
救急車で大阪府立病院救急センターに搬送されるが、そのまま意識不明の重体におちいる。
集中治療室に入って10日後、奇跡的に目覚める。
しかし、両親のことも、友人のことも、そして自分自身のことさえも、何もかもすべて、忘れていた。(5ページより)
医学的なことはわかりませんが、記憶喪失といってもタイプや症状はいろいろありそう。たとえば、僕は過去にテレビで、自分が記憶喪失であることを明るく打ち明ける人を見たことがあるのですが、本書を読む限り、著者の症状はもっと重たかったようです。
目のまえにある物は、はじめて見る物ばかり。なにかが、ぼくをひっぱった。ひっぱられて、しばらくあるく。すると、おされてやわらかい物にすわらされる。ぱたん、ぱたんと音がする。
いろいろな物が見えるけれど、それがなんなのか、わからない。だからそのまま、やわらかい物の上にすわっていると、とつぜん動きだした。外に見える物は、どんどんすがたや形をかえていく。(18ページより)
これは、車に乗せられて家に帰るときの描写です。このように著者は見るものすべてがわからず、それどころか家族や友人のことも、食べたり眠ったりする感覚までもがわからなくなっていたのです。
ちなみに著者は事故当時、大阪芸術大学の学生。一時は絵を描く能力すら退行したようですが、次第に感覚を戻し、人より時間がかかってしまったとはいえ、着実に才能を開花させていきます。
そして、そんななかで染色に傾倒し、卒業後は京都の「夢祐斎」(ゆめゆうさい)いう染工房に入社。染師の奥田祐斎に師事して下積みを積んだのち、草木染作家としてデビューすることになります。
2005年には独立して「優介工房」を設立。桜、桃、どんぐり、笹など、さまざまな植物での草木染を行い根強いファンを魅了しているのだとか。
つまり、ここでは紹介しきれない多くの苦難を乗り越えた末、無事に自分の進むべき道を見つけ、現在に至っているわけです。
もちろんその背後には、本人の並々ならぬ努力があったはずですが、同時に無視できないのが周囲の人々の支え。家族、友人、恩師などさまざまな人たちが、それぞれの立場から著者の現実を受け入れ、寄り添ってきたからこそ、彼はここまでたどり着くことができたということです。
本書を読んでいると、そのことがよくわかります。
そして最終的に著者は、事故前の過去に対する執着を捨て「あたらしい過去」を生み出そうと決意します。何年か前までは昔の自分に戻りたくて仕方がなく、どうしたら記憶が戻るのかと思い悩んでいたものの、気持ちが変わっていったというのです。
この境地こそが本書の核心であるため、今回は以下を「人生を変える一文。」と認定したいと思います。
今のぼくには失くしたくないものがいっぱい増えて、過去の十八年の記憶よりも、はるかに大切なものになった。楽しかったことや、辛かったこと、笑ったことや、泣いたこと。それらすべてを含めて、あたらしい過去が愛おしい。
(248ページより)
いちばん怖いのは、事故の前の記憶が戻ることだとすらいいます。なぜなら、そうなった瞬間に“いまいる自分”がなくなってしまう気がするから。これは過去を乗り越えない限り、行き着くことのできない発想であり、つまり読者はここまで読むと、著者の成長をはっきりと確認できるのです。
だからこそ、この世界に生きるすべての人が、それぞれの苦悩を乗り越えようとするとき、著者がたどってきたこのストーリーは、きっと力になってくれるはずです。
追記:終わりのほうに出てくる「恋をした」という500字程度の文章が、純粋でみずみずしく、最高に素敵です。ゆえに、この部分も必読。

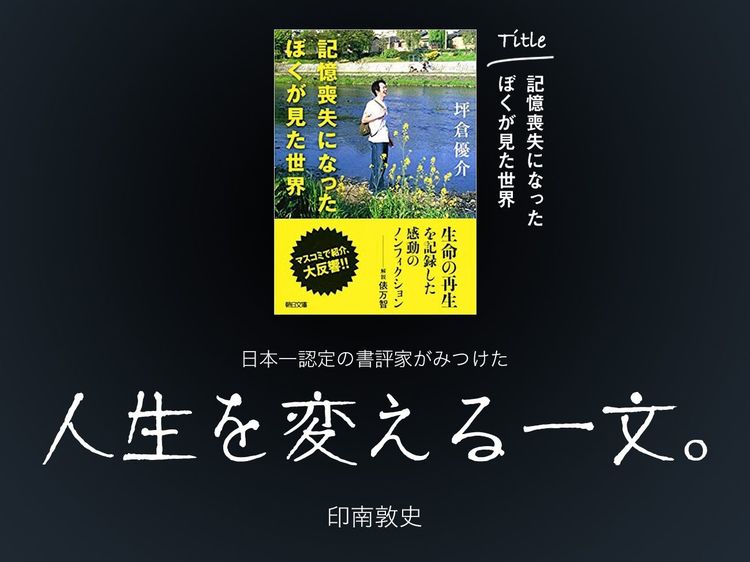
 印南 敦史
印南 敦史