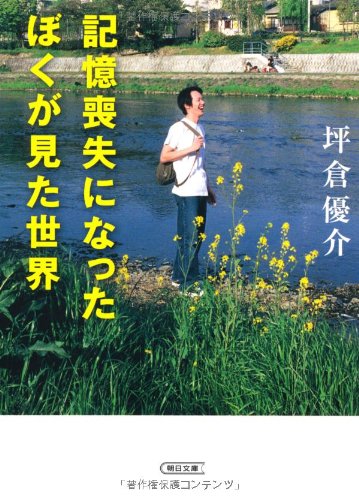読むのに1分もかからないシンプルな「一文」が、人生を変えてくれるかも。何かに悩んでいる時に、答えに導いてくれるのは「本」かもしれない。日本一書評を書いている印南敦史さんだからこそみつけられた、奇跡のような一文を紹介します。
人生を変える一文 -『 あたらしい過去が愛おしい。』-
こんにちは。姉妹サイト『WANI BOOKOUT』で「神は一文に宿る。」という連載を担当しておりました、作家・書評家の印南敦史と申します。今回からこちらに引っ越し、新たな切り口で新連載をスタートすることになりました。どうぞよろしくお願いします。
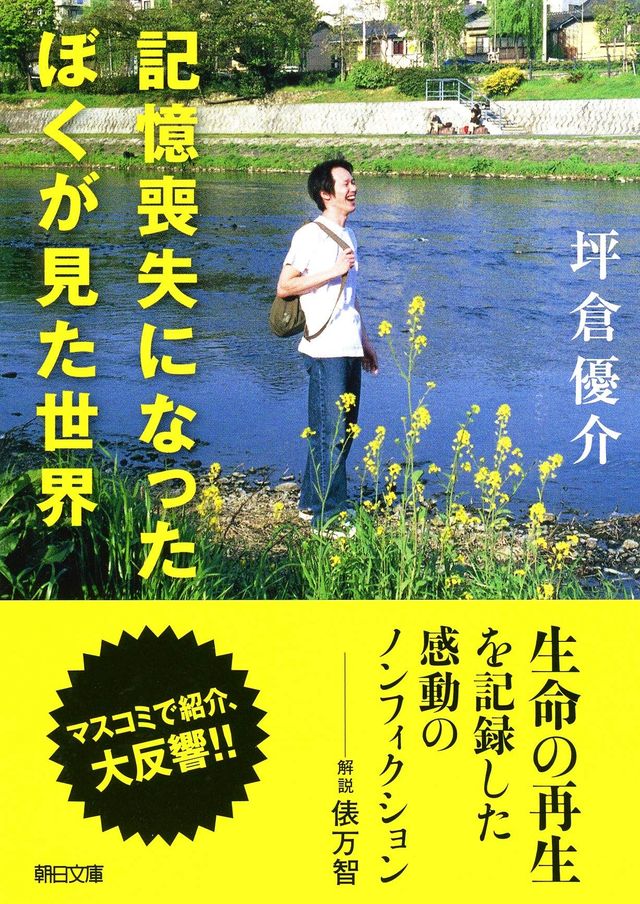
著者と似た経験をした小学4年生の春
というわけで、今回は小学生時代の話から。
小学4年生になった月の最終日曜日の夕方、僕は自転車で大怪我をし、生死をさまようことになりました。頭を強く打って20日間も意識不明だったというのですから、ほとんど死んだも同然です(三途の川は見てません。命を紡ぐのに忙しく、そんなものを見ている暇もなかったみたいです)。
医師からも「99%、命の保証はできません」と断言されていたといいますが、それでも奇跡的に助かったのですから、運には感謝しなければなりませんね。
ただ正直にいえば、本当につらかったのは、3カ月を経て退院し、社会復帰したあとでした。なにしろ頭を打ったので、同級生やその親、近所の人たちなどからも「あの子はもうダメだよねー」と、好奇の目で見られることになったのです。
大げさではなく、本当の話です。心ないことばを投げかけられたこともありました。でも、それは仕方がないことだとも考えていました。もし自分ではなく、クラスの他の誰かが同じ目に遭ったのだとしたら、僕もその子のことを変な目で見ていたかもしれないと思ったから。
とはいえ10歳になったばかりの子どもにとって、冷たい世間の目はなかなかキツかったわけです。
入院していたころ、意識が戻ったばかりの時期に、印象的な出来事がありました。面会謝絶のプレートが外され、友だちや先生がお見舞いに来てくれるようになったときのことです。
仲がよかった友人のN村くんが、僕が横たわるベッドの横に来るなり、心配そうな表情をしてこういったのです。
「僕のこと、わかる?」
本当に心配してくれていることがわかったので、笑顔で「覚えてるよ」と答えました。N村くんが帰ったあと、母は「記憶喪失だなんて!」と激怒していましたが、なにしろ頭を打ったのです。だから、そう思われるのはむしろ当然だろうと、当事者である僕は感じていたわけです。
いずれにしてもそんな経験があるからこそ『記憶喪失になったぼくが見た世界』(坪倉優介:著/朝日文庫)の前半は、ちょっとだけつらく感じました。著者と僕は同じ体験をしたわけではないけれど、それでも過去を思い出してしまったからです。

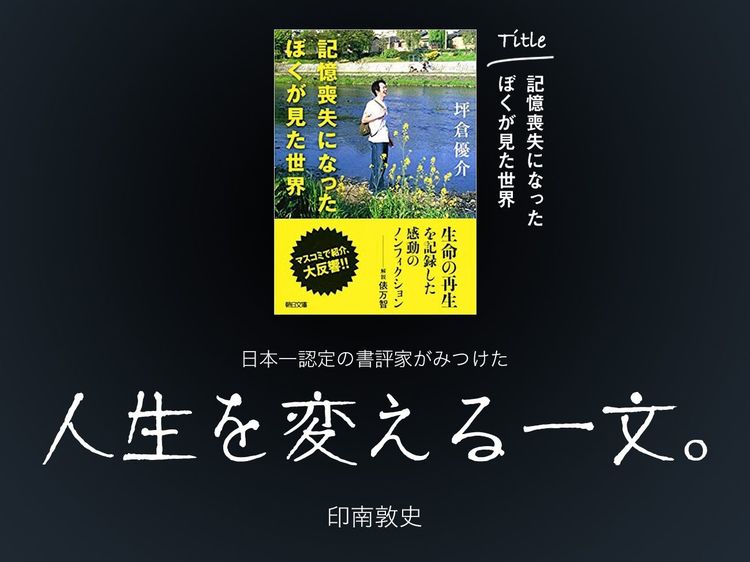
 印南 敦史
印南 敦史