バルカン半島を普通人の旅行日程とはあえて反対に回っていった樋口季一郎たち。半島の中で何を目撃し、考えていたのか。樋口季一郎本人の目線から、その時のことを詳細に読み解いていく回想録。
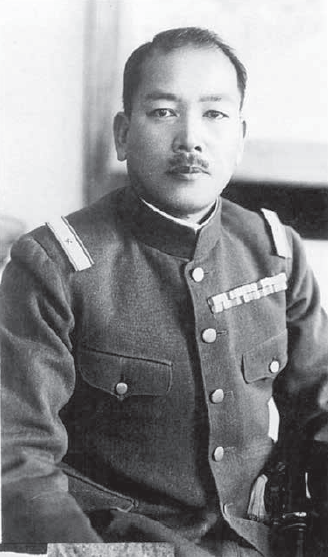
バルカン半島の旅はルーマニアから
大正十五年(1926)初夏、私は公使館の大谷書記生と同伴でバルカン半島への旅に上った。
大谷君の父君は工兵出身の退役少将であった関係で、私との間がよく、拙宅におけるいわゆる「招かれざる常客」の一人であった。彼は外語ロシア語科の出身であり、そのロシア語はなかなか正確であり達者であった。
きわめてデリケートな性格の持主で、むしろ文学者、芸術家肌であった。私にロシア文学の種々相をよく語り、私を啓発した。
私どもは、一般人の旅行日程とは反対の行き方をした。まずルーマニアへ、それから黒海経由トルコ、ブルガリア、ユーゴー・スラヴィア、ハンガリー、オーストリア、チェッコ・スロバキアを経てワルソーに帰ろうとするのである。
私どもはリュボーフ(レンベルグ)を経て、直路ルーマニアの首府ブカレストに到着した。ブカレストは小パリと呼ばれていた。否、ルーマニア人がそう呼んでいたのであって、田舎の東部バルカン地方ではたしかに立派な都会である。
そこの公園と王宮などを見物したが、たいした見ごたえはなかった。公園といえどもワルソーのラゼンキー公園と比べれば、問題なくラゼンキーのほうが上であった。この国の王室はその頃、相当に乱脈であって、へたをするとクーデターの第一歩を踏んでいた。

公使は私が大尉時代、参謀本部でよく見かけた武者小路氏であった。この夜、小西君(三等書記官)の案内で、そこの第一等のダンシングに案内された。そこではチャールストンを踊っていた。小西君は大変上手に踊った。
私は自重した。ワルソーへはこの踊りはまだ来ていない。この意味においてブカレストはたしかにプチ・パリである。パリとの文化交流が早いというわけか。ブカレストと新興国ポーランドの首都ワルソーとを比較すると、やはり後者は二ないし三倍の力を持っているのではなかったか。
国力もまた然りといい得るであろう。両国民ともになかなかの虚栄家であり、実力以上に自らを誇示する風がある。しかし、農民の勤勉力はポーランドのほうがはるかに勝っていると考えられた。それは田舎の道路の整備などで窺われるわけである。この国の物産は石油であり、ブカレスト北方地区を車行しても、その殷盛ぶりが見られるのであった。
この国はポーランドに比べ、バルカンの田舎に位置するだけ国防的にはよほど恵まれており、安全性は高いと観察された。しかし、この国の石油がかえって、この国の国防ないし独立を脅かしていた。第一次大戦後期、ドイツ帝国は一方には対露戦略の必要性からでもあるが、他方ブカレスト付近の石油に着眼し、外交的に同盟側に引き入れんとした。ルーマニアはあくまで「中立」を維持せんとした。
また、ロシアもルーマニアの中立を希望した。しかしドイツはそれに満足せず、ルーマニアは結局は同盟側に立たざるをえなくなったのであった。ここに大国ないし大勢力の中間に存在する国家の中立の困難が立証される。
ドニエストル河とドネープル河の中間の地域をベッサラビア州と呼ぶ。それは第一次大戦前ロシア領であったが、ロシア革命のどさくさに乗じ、ルーマニアはそれを自領に編入した。日本はこの国際協定に参加したが、久しくこれが批准を躊躇したものであった。
それはソベートロシアに対する気兼ねでもあったろうし、またルーマニアのやり方に不満でもあったからであろう。ペッサラビアにキシネフという小都がある。いつの時であったか、帝政ロシアがここで何千人というユダヤ人の大虐殺を行ったのであり、ロシア人は、いつもいう通りドーブルイ・チェロウェーク(善人)であるとともに、恐しく嗜虐性をも持っている。

