日中戦争の開戦前、1940年からイギリスと中国は手を組んで、日本が使用する暗号の解読に乗り出す。しかし、実際のところは協力関係が進まないままの状態だったので、イギリスは戦艦2隻を失うことになった。その裏にあった両国の思惑とは? 同盟国であっても決して油断してはならないことを、インテリジェンスヒストリー(情報史学)に詳しい山内智恵子氏が、ユ教授の「日中戦争」論をもとに解説。
「欲しいものは奪い取る」のがイギリス方式
1941年12月18日、米艦「タルサ」が積んできた中国向け武器貸与法物資を、イギリスが取ってしまうという事件があり、アメリカの現地担当者と蔣介石を激怒させています。
さらにすごいのは、イギリス情報機関が国民政府情報機関の暗号解読チームに協力を要請し、国民政府が応じると、中国が日本の暗号解読に使っている暗号鍵を巧みに突き止めてしまったことです。
当時、国民党の情報組織である国民党軍事委員会調査統計局(略称「軍統」)は、非常に優れた航空情報収集ネットワークを持っていました。浙江省と福建省の沿岸部に海空観測所を設置して、台湾・中国東部・日本本土に囲まれた区域の日本の船と飛行機を監視し、国籍・型・数・方向・速度、飛行機の場合は高度も、発見後3~5分のうちに本部に報告する体制です。
しかも、1939年後半には日本の軍事暗号解読に成功したので、日本の航空攻撃には事前に警報を出して住民を避難させることができたし、性能で勝る日本の戦闘機に対して、不利を補いながら戦うことができました。
イギリスは、対日開戦前の1940年から国民政府との暗号解読協力を行ってはいましたが、実際のところ、協力関係が進まないままの状態で対日開戦を迎えます。せっかく中国側が航空情報を提供しても、イギリスはなぜか使わず、なんの対処もしないままに日本の空爆を受けるようなことが続いたため、中国側の反発を買っていました。
実は、軍統の監視ネットワークは、日本軍偵察機がマレー沖を航行するイギリスの戦艦、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスの所在をつかみ、日本の爆撃機3隊がこれらを攻撃するために飛び立ったという情報を傍受していました。もし、英中のインテリジェンス協力がもっと行われていれば、イギリスは戦艦2隻を守れたかもしれないのです。
緒戦では敗北が続いたので、イギリスはようやく本気になり、1942年10月、イギリスの依頼で、中国人暗号解読チームがインドに送られました。イギリスはそれまでと違って、中国チームを温かくもてなし、あらゆる機材を提供し、中国チームが提供する情報に対しても大いに感謝の意を示しました。ところが、イギリスには中国側に隠していることがありました。

イギリスは中国チームが滞在している基地とは別に、自分たちだけの傍受基地を作り、中国側が解読していたのと同じ日本の秘密通信を受信していたのです。そして、中国チームが提供した報告と、自分たちが傍受した暗号通信を比較・分析することによって、中国チームが解読のために使っていた暗号鍵を解明しました。軍統の幹部らは、やがてこのことに気づき、イギリスへの憎悪を募らせました。
中国に分裂工作を仕掛けるイギリス
最も凄まじいのは、対日戦を戦っている最中に、イギリス情報機関が中国に対して分裂工作を仕掛けたことです。
SOEのジョン・ケズウィックは、広東省の陳策というゲリラのリーダーを支援していました。ケズウィックが中国特殊部隊を掌握したあと、陳が広東省の主席になるという噂が突然広まりました。国民党の幹部らは、イギリスの支援で広東が独立するのではないかという不安に襲われました。
蔣介石は1920年代に各地の軍閥を倒して、一応の統一を成し遂げましたが、地方によっては中華民国政府の統制があまり及ばず、独立性の強い省がいくつかありました。
ケズウィックは広東省だけでなく、雲南省でも独立工作を疑われるような行動を取っています。1942年2月にケズウィックが蔣介石とともに雲南省に行ったときのこと、ケズウィックは蔣介石に断りなく、雲南省政府主席の竜雲を訪問したいと要請しました。
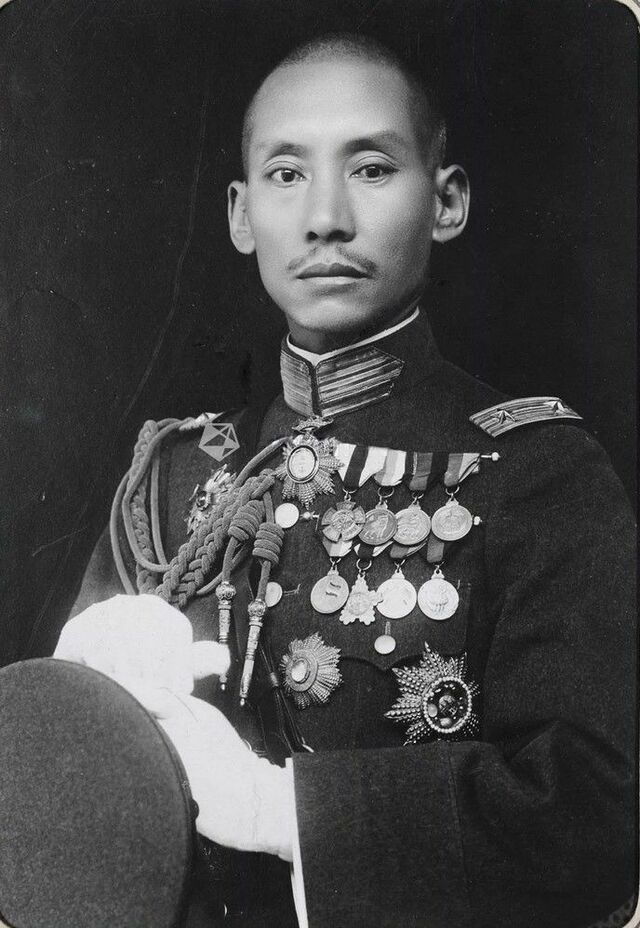
ケズウィック本人は、特に他意はなかったとあとで弁明しましたが、竜雲は蔣介石の部下というよりも、独自に活動している同盟者のように扱われていた人物であり、雲南省は実質的に、蔣介石政権ではなく竜雲の支配下にありました。
ビルマと地理的に近い雲南省の竜雲について、イギリスは以前から独立支援に関心を持っていたとユ教授は指摘しています。陳策のことがあるので、蔣介石がケズウィックへの不信感を一層募らせたことは言うまでもありません。


 江崎 道朗
江崎 道朗